『未来への警鐘 原発を問う』映画を観た後あなたは原発賛成に考えを変えますか?
『未来への警鐘:原発を問う』という邦題からは、ある種の批判的・警戒的なトーンを感じ取れるが、原題は『Nuclear Now(今こそ、原子力を)』。しかも原作は、アメリカの科学者Joshua S. Goldstein & Staffan A. Qvistによる共著『A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change(明るい未来――脱炭素社会のリアルな解決策)』である。
この日本語タイトルと原題、そして原作の内容を並べてみると、大きなズレを感じるだろう。
配給会社NEGAによると、本作は広島での上映を、地元の映画館に断られたという。各地の社会派の作品に日頃から積極的な劇場映画を観た上でパスだったらしい。日本では、広島・長崎の原爆による甚大な被害、そして福島第一原発事故のトラウマが今も色濃く残っている。現在もなお避難生活を続けている人たちがいるという現実のなかで、原発稼働に対する根強い反対意見があるのは当然のことだ。だからこそ配給側も、原題とは逆の意味とも言える邦題を選んだのだろう。
この映画を観るにあたっては、次の3つの問いを意識してはどうだろうか
1)原発は安全なのか
2)自分は科学を信じるか
3)映画に自分は洗脳されていないだろうか
原作の著者たちは、気候変動という地球規模の課題に向き合う中で、「現実的かつ短期間で実行可能な脱炭素化戦略」を模索している。再生可能エネルギーだけではスピードが足りないという問題意識から、彼らは原子力発電の再評価を主張する。つまり「原発=悪」という感情的反応ではなく、科学的・実務的視点からの提案というわけだ。
監督のオリバー・ストーンもまた、原子力を擁護するというよりは、あくまで中立的な立場を取ろうとしているように見える。作中では科学者たちの声に耳を傾けながら、冷静に原子力の可能性を掘り下げていく。後半に登場する小型モジュール炉(SMR:Small Modular Reactor)のくだりでは、廃棄物は20年に一度回収するだけ、という仕組みが語られる。その説明を聞いていると、原発という選択が地球温暖化を救うのだと、けっこう説得されてしまう。
本を読むより映像のほうが圧倒的に説得力があるし、音楽が感情を揺さぶる。そういう意味で、観客はストーン監督と同じように、原子力の未来に希望を感じてしまうかもしれない。
でも、日本人の私たちなら気づくだろう。この映画、都合の悪い現実にはあまり触れていないということだ。たとえば、福島第一原発で起きたメルトダウンや水素爆発。原発が吹き飛んだあの衝撃的な映像は存在しているのに、本作ではあえて使われていない。脱炭素社会の明るい未来を描くには、不要な不安を煽る映像をカットしているのは印象操作と言っていいだろう。
この映画のメッセージは明確だ。気候変動は絶望ではなく、科学と現実的な政策によって解決できる。感情やイデオロギーではなく、冷静な思考が未来を拓く、というわけだ。原作が提示した考えを、ストーン監督が映像として取材・構成し、届けたのがこの作品である。
さて、映画を観終えたあとで、あなたはどう感じるだろうか。
それでも原発には反対だと考えるのか。
それとも、地球温暖化を食い止める手段として、原発という選択もありだと受け入れるのか。
ぜひ映画を観て自分の目と頭で考えてみてはどうだろうか。(TA)
イントロダクション
気候変動に喘ぐ地球
人類が選ぶべき本当のクリーンエネルギーとは
自身のベトナム戦争体験をもとに描いた『プラトーン』(1986)と『7 月 4 日に生まれて』(1989)でアカデミー賞の監督賞を 2 度受賞したオリヴァー・ストーン監督が、「いかに気候変動を解決するか」について書かれたアメリカの科学者ジョシュア・S・ゴールドスタインの著書『明るい未来』を基に、原子力エネルギーを見直すドキュメンタリーを制作。
貧困国は急いで発電を進めていて、最も安く早く簡単な技術である石炭を使うが、石炭は世界中で1 年に 50 万人の死者をだす他、癌や肺気腫、心臓病などの影響を出している。経済の成長で、2050 年までに現在の 2~4 倍のクリーン電力が必要となるが、現実的に見て再生可能エネルギーではこのギャップは埋まらない。今、人類が選ぶべきエネルギーとは何か。
広島・長崎への原爆投下、チェルノブイリ原発事故、福島第一原子力発電所事故など、人類はこれまで被ばくによる被害を目の当たりにしてきた。だが、石油・ガス業界が率先して行ってきた原子力エネルギーに対する大規模なネガティブ・キャンペーンによって、核に対する恐怖心を煽られた一面もあると、オリヴァー・ストーンは指摘する。
地球が気候変動とエネルギー貧困の課題に直面する今、果たして「原発」は未来への伴となるのか。オリヴァー・ストーンの原子力に対する提案をどう受け取るべきか。世界に問う、衝撃のドキュメンタリー。
ストーリー
2017 年、トランプ大統領はアメリカをパリ気候協定から脱退させ、気候変動をでっち上げだとしたが、多くの人々は、再生可能エネルギーという形のクリーンエネルギーを選んだ。再エネへの世界の投資はおよそ 3 兆ドルに達し、太陽光は 8 割、風力は 5 割コストが下がった。だが、多大な努力と期待にもかかわらず、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、30 年以内に炭素排出をほぼ 100%カットしなければ、2050 年までに生態系と経済に深刻な被害が及ぶと示した。アカデミー賞の監督賞を 2 度受賞した社会派監督のオリヴァー・ストーンは、自ら原子力発電所などに出向いて取材をし、エネルギー源を見直すことに。
オリヴァー・ストーン監督 コメント
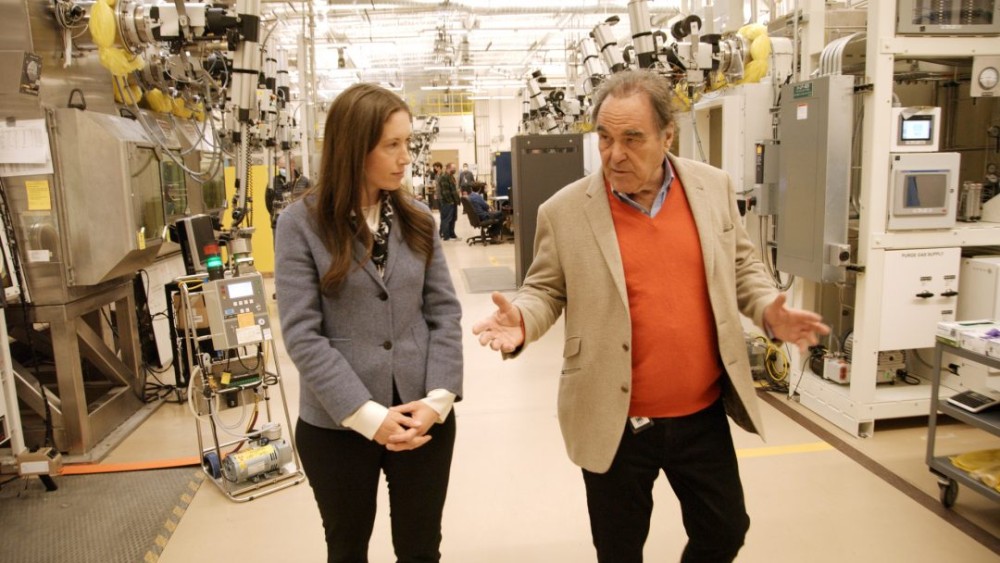
右がオリヴァー・ストーン監督
気候変動は、私たちにグローバルな共同体として、エネルギーを生み出す方法を新たに見直すことを強く迫っています。
では、二酸化炭素やメタンといった温室効果ガス、そして多くの国々で使われている石炭を大幅に削減しながら、何十億もの人々を貧困から救うにはどうすればよいのでしょう?
風力や太陽光発電のような“再生可能エネルギー”は確かにこの移行に貢献しますが、天気や地形によって制限されます。
私たちは転換すべきです――それも、早急に。
人類が貧困から繁栄へと向かい、科学の力でますます高まるエネルギー需要を克服していく軌跡は、私の考えでは、現代における最も素晴らしい物語です。
監督プロフィール
1946年生まれのアメリカ合衆国の映画監督・脚本家・プロデューサー。
ベトナム戦争の従軍経験を背景に、社会や政治に鋭い視点を向けた作品を数多く手がけてきた。『プラトーン』(1986年)でアカデミー賞作品賞と監督賞を受賞し、続く『ウォール街』(1987年)では金融業界の欲望と倫理を描き、『7月4日に生まれて』(1989年)で再び監督賞を受賞した。さらに、ケネディ暗殺を巡る陰謀を描いた『JFK』(1991年)、メディアと暴力を風刺した『ナチュラル・ボーン・キラーズ』(1994年)、監視社会の実態に迫る『スノーデン』(2016年)など、実在の事件や人物を題材に権力構造を批判的に描き続けている。




アップリンク吉祥寺ほか全国劇場にて8月1日(金)公開
監督・脚本:オリヴァー・ストーン
脚本:ジョシュア・S・ゴールドスタイン 音楽:ヴァンゲリス
2022 年 / アメリカ /105 分 / カラー /5.1ch/ 原題 "NUCLEAR NOW"/ 配給:NEGA
©2023 Brighter Future, LLC. All rights reserved

