『蝶の渡り』なんという豊潤なジョージア映画なのだろう
『蝶の渡り』は、ジョージアを代表する映画監督ナナ・ジョルジャゼ(1948)の新作にして、彼女のキャリアの集大成的な作品だ。
ジョージアが「映画の大国」と言われる所以は、1920年代にはロシア・アヴァンギャルドの影響を受けた芸術的意欲に富んだ作品が多く製作され、その後も、厳しい政治的抑圧下にありながら、自国の文化を誇りに思い、独自の表現を追求し続けたところにある。
そのジョージア映画『蝶の渡り』、この映画は、なんという豊潤な映画なのだろう。
まず目に飛びこんでくる色彩の豊潤さ。映画の舞台となるのは、古びた半地下の大きな部屋、調度品、壁紙、テーブルの上の食べ物、などなど色鮮やかというのではなく、装飾されたアンティックというのでもなく、生活の豊かさ、それは経済的な豊かさではなく、文化的豊かさ、精神的豊かさを感じさせる。
そして、その部屋に存在する人々の精神の豊潤さ、それは高貴な精神ではなく、毎日続いてきたそれも変化に富んだ毎日の連続を苦しいことや悲しいことがあっても楽しむという精神を持つ豊潤さだ。
映画の中では、何度か1991年5月にソ連から独立した際に倒されるレーニン像が映される。
物語は、独立から27年後。画家コスタは、祖父母の代からの古びた家の半地下に暮らしている。そこに集まるのは、かつての芸術家仲間たち。そこに、コスタの昔の恋人ニナが戻ってきて、コスタの絵を買いにきたアメリカ人コレクターが、なんと彼女に一目惚れと展開していく。
登場人物たちの精神は先に述べたように豊潤であり、そしてなによりも自由だ。
かのフェデリコ・フェリーニは「ジョージア映画には、私を不覚にも泣かせる全てがある」と称賛したと言われている。
まさに『蝶の渡り』がそうである。(TA)
【アップリンク吉祥寺 上映後トーク開催決定】
1月25日(土)13:05の回上映終了後
登壇者:はらだたけひでさん(ジョージア映画祭主宰/画家)

イントロダクション
小国ながら“映画の王国”と呼ばれるジョージア(旧グルジア)。西と東の交差点に位置し、また、旧ソ連の構成国とい
う複雑な歴史のなかでも、独自の文化を培ってきたジョージアの映画は、オタール・イオセリアーニら数々の名監督を
輩出、世界的巨匠フェデリコ・フェリーニが「私を不覚にも泣かせる全てがある」と称賛したことでも知られていま
す。そのジョージア映画を代表する女性監督、ナナ・ジョルジャゼの待望の新作にして、彼女のキャリアの集大成的な
傑作が『蝶の渡り』です。
笑いあふれるドタバタ的展開を交えながらも、未来に行き詰まり、生き抜くために「渡り」をするジョージア人の姿を
蝶に託す、味わい深い演出。今もジョージア人の心に残るアブハジア戦争の痛みや、ディアスポラ(民族離散)の悲し
みをも、ジョージア独特の“陽気な悲劇性”で描ききります。共同脚本、美術、撮影、衣装、音楽など主要スタッフに
は、ジョージア第一線の文学者、アーティスト、作曲家が揃い、劇中に登場する数々のジョージア現代絵画も見逃せま
せん。どこかへ渡らなくてはならない蝶もいれば、とどまることを選ぶ蝶もいる。どちらにもきっと次代につながる風
は吹いているはずだ。悲しいはずなのに明るく祝祭的で、未来への楽観と希望に満ちて。ジョージアでも国外でも、批
評家にも観客にも、感動的に受け止められた本作。特にエモーショナルな反応が巻き起こったというラストシーンま
で、どうぞお楽しみください。
ストーリー
ジョージア。1991 年。
ソ連からの独立の夢が近づき、希望に満ちた<どんちゃん騒ぎ>で新年を迎える若者たち。
ソ連崩壊後、ジョージアは独立を宣言するものの、たくさんの命が奪われることになる。
ジョージアはロシアとの戦争で国土の一部を喪失。アブハジアと南オセチアは今もロシア占領下にある......
27 年後。
画家コスタは、祖父母の代からの家の半地下に暮らし、そこには芸術家仲間たちがいつも集まっている。
才能があってもうまくいかない。仕事がない。世間に認められない。
アートに関心を持つ人は日に日に減り、コスタは、明日の電気代にも困るほどだ。
新年を迎えようとしているある日。今日も今日とて......。
コスタの家に、音楽家のミシャとムラ、衣装や帽子を作っているロラ、今は修道院にいるナタも集まっている。
そこに、コスタ最愛の女性である元バレエダンサーのニナが、彼のもとに戻ってくる。放蕩娘の帰還だ。
そんな時、タソが、コスタの絵を買いたいというアメリカの美術コレクターを連れてくる。
コレクターのスティーヴは、すべてのコスタの絵を買い取りたいと言うが、
コスタは「蝶の渡り」だけは、いくらお金を積まれても手放そうとしない。
ナナ・ジョルジャゼ監督インタビュー

――最初に、この映画を作ろうと思ったきっかけを教えていただけますか?
これは私の友人たちに捧げた映画なんです。私自身がこうした友人たちに囲まれて生きてきました。私は若い頃、美術学校で建築家の勉強をしていたのですが、当時から多くの芸術家の友人がいました。画家だけでなく音楽家やダンサーや、いろいろな芸術を志す友人たちがいて、映画のようにいつも一緒にいて、切磋琢磨して、苦しい時も助け合って生きてきました。
独立の後の90年代の戦争は、私たちの世代、そして私たちの子供たちが実際に経験したものです。この戦争でたくさんの人が亡くなり、国外に移住した人もいます。ジョージアはいつもロシアの脅威にさらされていましたから、移住という手段をとるしかいない人たちもいたのです。友人たちの話をすると、彼らの中にはとても才能豊かな人がいました。しかし、戦争があり、そして戦後の大変な状況の中で、彼らは自分たちの才能が誰からも必要とされないと感じて自信をなくしました。それで国外へと移住していったのです。そこから「移住」というものをテーマにしようと思いました。私たちはこれまでどう生きてきたか。それを映画にして友人たちに捧げたいと思ったのです。
――監督は、独立当時、40代を迎えていましたが、独立直後のご自身の気持ちを端的に語るとしたら、どのような気持ちだったのでしょうか?
最初は幸せな気持ちでしたが、ロシアがジョージアの2つの地域——アブハジアと南オセチア——で戦争を始めたため、その気持ちは長くは続きませんでしたね。
――この映画は、いつからいつまでの物語ですか?
ジョージアでは他の正教圏と同じように、ユリウス暦も使います。(グレゴリオ歴・西洋歴の)1月1日にクリスマスツリーを出して新年を祝うのです。ツリーはユリウス暦のクリスマスまで出しておきます。クリスマスを祝うのは1月6日から7日の夜。ですから、映画の冒頭、若い頃の主人公たちが祝っているのは1月1日の新年。そこから27年後の新年になり、ラストはその年の12月31日。年越しを祝うシーンです。
――ジョージア語の原題は「蝶たちの強制移住」ですが、このタイトルに込められた思いを教えていただけますか?
このタイトルは日本の方にも共感してもらえるのではないかと思います。というのも、私は俳句——高度に洗練された芸術の形態です——にインスパイアされて、このメタファーを思いついたからです。日本の俳句や短歌に私はいつも魅了されてきました。短く簡潔で1行の中に大きな世界が広がっている。そんなタイトルにしたいと思ったんです。
同時に、トゥシェティという映画にも登場する地域に特別な蝶がいて、それは渡りをするのだけれど、風に乗ってうまく戻ってこないと死んでしまう、ということを知りました。映画の中ではイタリア人学者がトゥシェティでその蝶を保護しなければならないと言いますよね。国外に出るのは良いことでもありますが、帰るべき故郷があるということは非常に重要なことだと思います。
――ラストシーンに「ジョージア 母の像」を入れた意図を教えてください。
ラストシーンは、昔から個人的に好きな通りで撮影しました。5世紀に作られたというトビリシで一番古い教会があり、そこから見上げると像が見えます。ジョージア 母の像は、誇り高いジョージアの象徴です。私はたくさんの国を旅してきましたが、あの像には特別な思い入れがあるのです。
――ナタが少年にカメラを渡すラストシーンは忘れられません。これからの世代にナナさんが伝えたいことは?
前世紀の初めに生きた著名なジョージアの詩人で作家のイリア・チャヴチャヴァゼの言葉を一つ——私が翻訳したものですが——たとえ今、幸運に恵まれずとも、心だけは失うな。行く手には希望と明るい未来が待っている。
残念ながら、映画も含め芸術や文化は世界を変えることはできません。けれど、人々に何かを考えさせることができると信じています。直接ではないけれど、人の心に残り、人の内面世界を広げていくのです。内面世界が小さいと人は支配されてしまいます。さまざまなことを知り、他者を知り、他の文化を知り、関心を持ち、内面世界を広げていく。内面世界が広く大きければ理解が生まれ、憎しみに支配されることはありません。政治的な要因などで世界が変化していったとしても、芸術は残っていくと信じています。(インタビュー:武井みゆき 通訳:児島康宏)


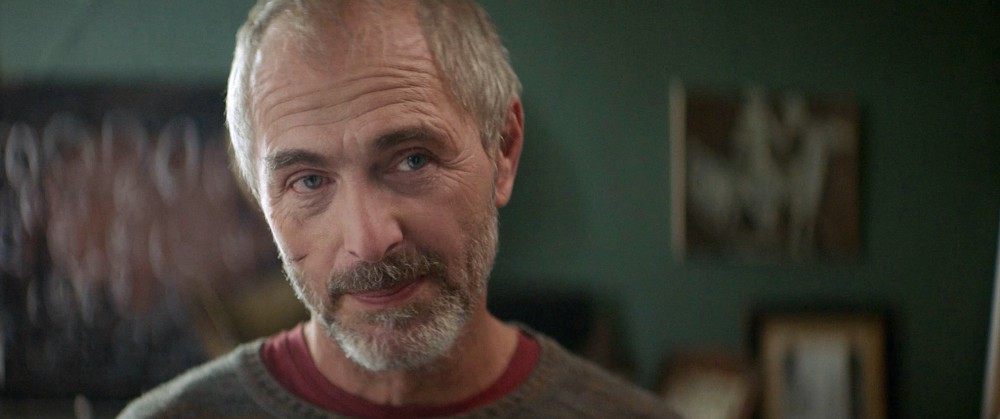

アップリンク吉祥寺ほか全国劇場にて公開
監督:ナナ・ジョルジャゼ
出演:ラティ・エラゼ、タマル・タバタゼ、ナティア・ニコライシヴィリ
配給:ムヴィオラ
2023年|ジョージア|89分|カラー|ジョージア語
© STUDIO-99

